2025年6月17日、ロサンゼルス・ドジャースのマウンドに立った大谷翔平選手の姿は、まさに別人でした。
663日ぶりの投球復帰を果たした彼のフォームには、2023年までとは明らかに異なる変化が見られたのです。
私はアスレティックトレーナーとして8年間、整形外科での臨床経験5年、大学トレーニングジム5年、そして少年サッカーや社会人ラグビーでのチームトレーナーとして現場に携わってきました。その経験から見ても、大谷選手の今回のフォーム変更は、スポーツ医学的に非常に興味深く、かつ理にかなった進化と言えます。
本記事では、日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー(JSPO-AT)として
大谷選手の投球フォーム変化を科学的根拠に基づいて分析し
我々一般の野球愛好者やトレーナーが学ぶべき点について考察していきます。
2度目のトミージョン手術からの復帰:医学的背景
手術の革新性と成功率の現実
大谷選手が2023年9月に受けた手術は
従来のトミージョン手術とは異なる「インターナルブレース併用のハイブリッド手術」でした。
執刀したエルアトラシュ医師が「完全に最初とは異なる手術」と表現したこの術式の特徴は以下の通りです:
- 健康な靭帯組織を温存しながら新しい腱移植を実施
- 内部ブレース技術で靭帯を補強し、回復期間を短縮
- 従来12-18ヶ月の回復期間を実質10ヶ月で投球復帰を実現
ここで注目すべきは、2度目のトミージョン手術の成功率です。
一般的に1回目の成功率が約80%であるのに対し、2回目は約61%まで低下することが知られています。
さらに、二刀流選手での2回目復帰は史上初の症例であり
大谷選手のケースは医学的にも極めて貴重な事例となっています。
肘損傷の根本原因:「量×質×回復力」の複合問題
私がトレーナーとして現場で見てきた肘損傷の多くは、単一の原因ではなく複合的な要因によって発生します。
野球選手の肘損傷は「量×質×回復力」の掛け算で表現することができ、大谷選手の場合も例外ではありませんでした。
量的要因
- 投球数の多さ(年間投球数とイニング負荷)
- 登板間隔の短さ(中4日ローテーション)
- 二刀流による年間通しての身体負荷
質的要因(バイオメカニクス)
- 2023年までの腕の角度低下(45度→34度)
- リリースポイントの年々の低下
- 特定の球種による同一部位への過負荷
回復力の限界
- 二刀流による回復時間の制約
- 打者としての負荷が投手回復を阻害
フォーム革命の核心:セットポジション→ワインドアップ
最大の変化とその生体力学的意義
大谷選手の2025年シーズン最大の変化は、投球フォームの根本的再構築でした。
具体的には:
2023年まで(手術前)
- 常にセットポジションのみ使用
- 静止した姿勢からの投球
- 下半身のエネルギー利用が限定的
2025年(復帰後)
- フルワインドアップを導入
- 左足のドロップステップで助走距離確保
- 肩を打者正面に向けた構えから始動
この変更について、私は特に運動連鎖の観点から非常に合理的だと感じています。
実際に大学のトレーニングジムで投手の指導を行う際
私は常に「下半身から始まる運動連鎖」の重要性を説明してきました。
実体験から見る運動連鎖の重要性
大学トレーニングジムでの指導経験から、一つの印象的な事例をお話しします。
右肘に軽い痛みを訴えて来た大学生投手がいました。
フォームをチェックすると、上半身主導で投げており、下半身の力が全く活用されていませんでした。
そこで、まずワインドアップモーションから始まる基本的な投球動作を再指導したところ
わずか2週間で肘の痛みが軽減し、同時に球速も回復。
この経験から、全身の運動連鎖がいかに重要かを実感しました。
大谷選手のワインドアップ導入も、まさに同じ原理に基づいています
1. 推進力の向上
- ドロップステップにより体重移動距離が増加
- 下半身→体幹→上肢への運動連鎖を効率化
- 腕だけでなく全身の力を活用
2. 肘への負担軽減メカニズム
- 全身のバネを使うことで腕の負荷を分散
- より自然な投球リズムの獲得
- 急激な力の発生を抑制
腕の角度調整:戦略的な最適化
リリースポイントの復活
大谷選手のもう一つの重要な変化は、リリースポイントの調整です:
- 2021年:約186cm
- 2023年:約173cm(低下傾向)
- 2025年:約183cmに回復
この変化について、私の整形外科での臨床経験から重要な知見があります。
肘の内側側副靭帯(MCL)損傷の患者を数多く診てきましたが
リリースポイントが低い投手ほど、肘への横方向の負荷が大きくなる傾向がありました。
アームスロットの戦略的調整
専門家分析による変化:
- 2021年:約45度(オーバーハンド)
- 2023年:約34度(スリークォーター寄り)
- 2025年:34度前後で安定化(意図的な調整完了)
この角度変化には医学的根拠があります。
私が大学トレーニングジムで野球部の投手を指導していた際、選手の投球フォームを詳細に分析する機会がありました。
その経験から、腕の角度は単に「高い方が良い」というものではなく、個々の身体特性と投球目的に応じた最適解が存在することを学びました。
大谷選手の場合、34度前後の角度は
- 横変化球(スイーパー、シンカー)の効果最大化
- 肘の内側側副靭帯への負荷パターン変更
- 制球の一貫性向上への寄与
これらのメリットを考慮した戦略的な選択と言えるでしょう。
球種革命:シンカー13.7%の衝撃
復帰登板での球種配分変化
大谷選手の復帰で最も注目すべき変化の一つが、シンカー(ツーシーム)の積極活用です:
| 年度 | シンカー使用率 | フォーシーム | スイーパー |
|---|---|---|---|
| 2022年 | 3.7% | 主力 | 主力 |
| 2023年 | 6.5% | 主力 | 主力 |
| 2025年 | 13.7% | 35.6% | 35.6% |
この変化について、私はアスレティックトレーナーとしての経験から重要な意味を感じています。
コンディショニング指導において、同じ動作パターンや負荷ばかりを継続していると
特定の筋群や関節に過度なストレスが集中し、オーバーユース症候群のリスクが高まります。
そのため、私は常に選手たちのトレーニングプログラムに「負荷の多様性」を取り入れることの重要性を重視してきました。
野球においても同様で、特にメジャーレベルでは打者の分析能力が極めて高いため
投手側も常に新しい武器を模索する必要があります。
大谷選手のシンカー増投は、まさにこの戦略的多様性の表れと言えるでしょう。
スイーパーの質的進化
復帰後のスイーパーにも注目すべき変化が見られました
2023年(手術前)
- やや遅く大きな曲がり
- 制球に不安要素
2025年(復帰後)
- 球速向上により曲がり幅が小さく鋭い軌道
- 2022年レベルのキレが復活
- 「メジャー最高級のスイーパー」との評価復活
この変化は、フォーム調整による運動連鎖の改善が直接的に球質向上につながった好例です。
実戦成績と今後の展望
段階的復帰プログラムの成功
大谷選手の復帰は、医学的に非常に慎重かつ科学的なアプローチで進められました:
復帰登板の詳細データ:
- 第1戦(6/17 vs パドレス):1回・1失点・28球
- 第2戦(6/23 vs ナショナルズ):1回・0失点・初奪三振2個
- 第3戦(6/28 vs ロイヤルズ):2回・0失点・101.7mph自己最高記録
- 第4戦(7/5 vs アストロズ):2回・0失点・3奪三振
累積成績:6イニング・防御率2.25・球速平均97-99mph
特に注目すべきは、101.7mphというメジャー自己最高球速の達成です。
手術前より2-3mph向上しているという事実は、フォーム改造の成功を如実に示しています。
課題と将来性
ただし、現時点では課題も残されています。
高木豊氏(元プロ野球選手)が指摘したように、「球速こそ凄いが、本来ピッチャーの160キロと野手の160キロは質が違う」という点は重要です。
私の整形外科での経験から、手術後の選手が完全な球質を取り戻すには
筋力回復だけでなく、神経系の再適応も必要であることがわかっています。
大谷選手の場合も、今後さらなる調整により、真の球威が戻ってくると予想されます。
専門的視点から見る問題点と改善課題
制球面での技術的課題
アスレティックトレーナーとして復帰初期の投球を分析すると、いくつかの技術的課題が浮かび上がります:
1. ストライク率の低下
初登板での28球中16球(57.1%)というストライク率は、メジャーリーグ平均の約64%を大幅に下回っています。
これは以下の要因が考えられます:
- 新しいフォームへの神経系適応不足:ワインドアップ導入により、従来の運動パターンが変化
- リリースポイントの微調整期間:約10cmのリリース位置変化に対する感覚調整
- 球種配分変更による制球感覚の混乱:シンカー使用率急増(6.5%→13.7%)への適応
2. バイオメカニクス的リスク要因
フォーム変更に伴う潜在的リスクとして、以下の点を注意深く監視する必要があります:
腰椎への負荷増大: ワインドアップモーションでは、従来のセットポジションより腰椎の回旋角度が増加します。私が大学トレーニングジムで野球部を指導していた際、ワインドアップでの投球動作において腰椎過回旋により腰痛を発症した投手がいました。大谷選手の場合、打者としての負荷も加わるため、腰椎への複合的ストレスが懸念されます。
肩甲骨周囲筋群の協調性: 新しいフォームでは肩甲骨の動的安定性がより重要になります。ワインドアップでの腕の大きな動きに対して、肩甲骨周囲筋(棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋)の協調的収縮が必要ですが、これが不十分だと肩関節の instability につながる可能性があります。
球質改善への医学的考察
神経筋再教育の重要性: MCL再建術後の選手において、私が最も重視するのは神経筋制御の回復です。手術により固有受容器(関節や筋肉の位置感覚を司る感覚器)が一時的に機能低下するため、以下のような段階的アプローチが必要です:
- 基本的固有受容感覚の回復(術後3-6ヶ月)
- 動的安定性の獲得(術後6-12ヶ月)
- 競技特異的動作の精緻化(術後12-18ヶ月)
大谷選手の現在の状況は、まさに第3段階にあたり、球速は回復したものの
微細な制球や球質の調整が今後の課題となります。
長期的負荷管理の課題
二刀流特有のリスク分析
1. 疲労蓄積パターンの複雑化
- 打撃による下半身疲労が投球フォームに与える影響
- 走塁時の肩甲帯への負荷が投球に及ぼす影響
- 守備機会の少なさによる動的バランス感覚の維持
2. 回復時間の制約
一般的な投手の場合、登板翌日は完全休養が可能ですが
大谷選手の場合は指名打者として出場するため、真の意味での完全休養日が限定されます。
これは以下のリスクを伴います:
- 微細な炎症の慢性化
- 筋疲労の蓄積による代償動作の発生
- 神経系の過負荷による反応時間の低下
改善提案:スポーツ医学的アプローチ
1. 投球前ウォームアップの最適化
ワインドアップ導入に伴い、従来より大きな可動域が必要となるため
以下の要素を重視したウォームアップが必要です:
- 動的ストレッチング:肩甲胸郭関節・胸椎・股関節の可動域確保
- 神経筋活性化:深層筋(ローテーターカフ、深層腹筋群)の予備収縮
- 運動連鎖パターンの確認:軽負荷でのワインドアップ動作反復
2. 負荷モニタリングシステムの構築
私がチームトレーナーとして推奨するのは、以下の多面的評価システムです:
- 客観的指標:球速、回転数、リリースポイントの一貫性
- 主観的指標:疲労感、違和感の詳細な記録
- 生理学的指標:心拍変動、血中乳酸値、CK値
- バイオメカニクス指標:肘・肩の関節角度、地面反力
3. 段階的負荷増加プロトコル
現在のドジャースのアプローチは医学的に適切ですが、以下の点でさらなる最適化が可能です:
現在:1イニング→2イニング→(段階的拡大)
提案:球数+イニング数+投球間隔の3次元的管理
例:
第1段階:25球・1イニング・週1回
第2段階:40球・2イニング・週1回
第3段階:55球・3イニング・中6日
第4段階:70球・4イニング・中5日
最終段階:90球・6イニング・中5日
バイオメカニクス的最適化の余地
腕の角度に関する詳細分析
現在の約34度という腕の角度は、横変化球には適していますが、以下の点で改善の余地があります
肘への負荷分散: 理想的には、球種によって微細な角度調整を行うことで、MCLへの負荷を分散できます。
- フォーシーム:37-40度(やや高め)
- スイーパー:32-35度(現在の角度)
- シンカー:35-38度(中間)
リリース一貫性の向上: 私の指導経験では、リリースポイントの前後ブレが5cm以内に収まることが、制球安定の目安となります。現在の大谷選手は復帰初期でブレが大きい可能性があり、これは以下の方法で改善可能です:
- 視覚フィードバック訓練:ビデオ分析による即座のフォーム確認
- 感覚統合訓練:目を閉じた状態でのシャドーピッチング
- 標的精度訓練:段階的に標的サイズを縮小する練習法
アスレティックトレーナーとしての総合評価
成功要因の多角的分析
8年間のトレーナー経験から見て、大谷選手の復帰成功には以下の要因が大きく寄与していると考えています:
1. 科学的アプローチの徹底
- エルアトラシュ医師の革新的手術技術
- バイオメカニクス研究に基づくフォーム改造
- 段階的復帰プログラムの完璧な実行
2. 本人の特異な能力
- 異常なまでの身体認識能力
- フォーム変更への適応力
- メンタル面での強靭さ
3. 組織的サポート体制
- ドジャースの潤沢な医療リソース
- 長期的視点に立った投資戦略
- チーム一丸となったバックアップ
次世代選手への教訓
大谷選手のケースから、我々トレーナーや指導者が学ぶべき点は多岐にわたります:
フォーム設計の新原則:
- 下半身主導の運動連鎖構築
- 肘への負荷分散システム
- 適応的フォーム変更の重要性
投球管理の進化: 従来の一律的な球数制限から、個別最適化された負荷管理への転換が必要です。これには、バイオメカニクス分析による個人別リスク評価や、リアルタイム疲労モニタリング、多角的な身体状況把握が含まれます。
専門的サポートの必要性: 特に二刀流選手の場合、打撃による疲労が投球に与える影響の定量化や、シーズン通しての負荷バランス調整、専門的メディカルチームの配置が不可欠です。
業界への提言と今後の展望
トレーニング現場への応用
私が現在も関わっているトレーニング指導において、大谷選手の事例から得られた知見を積極的に活用しています:
具体的な改善点
- バイオメカニクス分析の導入(可能な範囲で)
- 運動連鎖を重視したフォーム指導
- 負荷と回復のバランスを重視したプログラム設計
- 多様性を重視した球種・技術指導
指導者育成の重要性: 今回の大谷選手の成功事例は、専門知識を持った指導者の重要性を改めて浮き彫りにしました。アスレティックトレーナー資格の普及や、バイオメカニクス理解の必須化、医学的知識を持った指導者の養成が急務です。
野球界全体への影響
大谷選手の復帰成功は、野球界全体に以下の影響を与えると予想されます
- 怪我予防投資の重要性認識:短期的な成果よりも長期的な選手の健康を重視する風潮の拡大
- 科学的アプローチの標準化:データに基づいた指導法の普及
- 選手価値の長期的視点:即戦力よりも将来性を重視した育成方針の浸透
まとめ:成功と課題を併せ持つ歴史的復帰
大谷翔平選手の2025年復帰は、単なる個人的成功を超えて
スポーツ医学とトレーニング科学の新たな可能性を示した歴史的事件でした。
セットポジションからワインドアップへの転換、戦略的な腕の角度調整、球種配分の最適化
そして101.7mphというメジャー自己最高球速の達成。
これらすべてが、科学的根拠に基づいた計画的なフォーム改造の成果です。
しかし、アスレティックトレーナーとしての専門的視点から見ると、成功の裏には解決すべき課題も多く残されています。
制球面での技術的調整、球質の完全回復、長期的な負荷管理、そしてバイオメカニクス的最適化など、今後も継続的な監視と改善が必要です。
私がトレーナーとして最も印象深く感じるのは
大谷選手とドジャースが「目先の結果よりも長期的な健康」を最優先に考えた点です。
この姿勢こそが、真の成功を導いた最大の要因と言えるでしょう。
今後の注目ポイント:
- 制球率の段階的改善(目標:65%以上)
- 球質の完全回復(神経筋制御の精緻化)
- 負荷管理プロトコルの最適化
- 二刀流特有のリスク要因への対応
現在も技術的課題は残されていますが、フォーム改造の基盤は完成しており
医学的・科学的アプローチによる段階的改善が期待されます。
二刀流選手の持続可能性を証明し
次世代のスーパースター育成の新基準を確立した大谷選手の復帰は成功例としてだけでなく
改善すべき課題も含めて、スポーツ医学の発展に大きく寄与する事例として記憶されることでしょう。
我々指導者・トレーナーにとっても、この事例から学ぶべき点は多く
成功要因だけでなく潜在的リスクや改善課題も含めて理解し、今後の選手育成に活かしていく責任があります。
科学的アプローチと長期的視点、そして継続的な問題解決により
より多くの選手が健康的に競技を続けられる環境作りに貢献していきたいと思います。
関連記事
執筆者情報
エビ(Ebi LIFE | えびちゃんの気ままライフ 運営)
- ウイスキー・ゲーム・スポーツ観戦愛好家
- 日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー(JSPO-AT)
- 健康運動指導士
- トレーナー歴8年(整形外科5年、大学トレーニングジム5年、チームトレーナー4年)
本記事の分析は、最新のスポーツ医学知見と筆者の実務経験に基づいて作成されています。


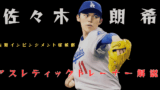
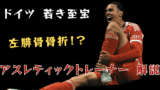

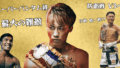
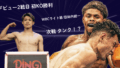
コメント